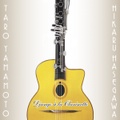Hikaru’s BLOG
Welcome to Hikaru’s Home Page
This web is oldest Japanese site of bluegrass music.
ShareTweet
16981631 visitors have come to this site since 26th April 1996.
BLOG
2014/12/21 Chicago Dukes @ 新宿三丁目呑者家銅鑼Update : 2014/12/20 Sat 01:57
急遽ギターのトラでお座敷が掛かりました。行ってきます。
写真は5月に新宿銅鑼でご一緒した時。

昭和の匂いUpdate : 2014/08/08 Fri 16:14
昭和37年〜昭和44年ごろ、大阪府豊中市大黒町というダウンタウンに住んだことがあります。3歳から9歳の頃です。なぜか、その頃の記憶が強く残っています。
そのあたりは、阪急宝塚線庄内駅・三国駅と阪急神戸線神崎川駅を頂点とした三角形の真ん中あたりにあって、風向きによっては、当時汚水路になっていた神崎川の悪臭が、風通しの良い長屋の食卓にまで漂ってきました。僕らの街は川っぷちという歌もありましたが、そこは町工場も多く、金属が焼けたような臭いも町に染み付いていました。ドブ川は毎日水面の色が変わりました。
2014/12/07 Gypsy Jazzセッション @ 新宿三丁目呑者家銅鑼Update : 2014/09/17 Wed 21:11
約1年続いているこの企画、この日はホーンプレイヤー無しで2ギター+ベースのトリオで演奏します。
新宿3丁目の銅鑼にて、日曜日昼間、なんとノーチャージ・持ち込み自由のライブです。
13時から対バン有りで2回ステージの予定です。
・遠藤昭浩 (guitar)
・長谷川光 (guitar)
・新井健太郎 (contrabass)
お時間ご都合付けば、日曜午後の新宿、トラッドでアコースティックなジャズを聴きにいらっしゃいませんか。
2014/12/05 Chicago Dukes @ 矢切PiccolinoUpdate : 2014/10/14 Tue 09:38
10月に一度お邪魔しました。北総線矢切駅前の可愛らしいお店でのライブです。いわゆるトラでギター弾きます。Chicago Dukesさんは名前の通りシカゴ系ジャズを演奏するベテランバンドです。ふだん演奏できる機会の少ないジャズを楽しませていただきます。
19:15スタート 40分3ステージ
河上衛(コルネット)、春田豊(クラリネット)、長谷川光(ギター)、大田裕三(ベース)
Piccolino 松戸市下矢切145
写真は5月に新宿銅鑼でご一緒した時。

2014/12/04 スヰング評議会 @ 西荻窪 ミントンハウスUpdate : 2014/09/17 Wed 08:05
営業時間 19:00〜23:00
演奏時間 19:30~22:30 (たぶん、この間に3ステージ)
チャージ ¥2,000.-
都下トラッドジャズの殿堂のひとつ、西荻窪のミントンハウスにて、いわゆるトラで演奏します。
松本耕司さん(tb)、菅野淳史さん(tp)を中心としたカルテットの模様です。